|
サイエンスカフェ in 名古屋 <番外編> 2010年7月25日、8月01、20、21、22日 いずれも、午後2時から (約90分間) |
夏休み、親子実験教室
液晶で遊ぶ、液晶を学ぶ
|
話題提供者 : 片山 詔久 氏 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 (専門:分子分光学) |
 |
|
サイエンスカフェ in 名古屋 <番外編> 2010年7月25日、8月01、20、21、22日 いずれも、午後2時から (約90分間) |
|
話題提供者 : 片山 詔久 氏 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 (専門:分子分光学) |
 |
 5日間の連続講座でありましたが、夏休みの期間中の主に週末に開催し、少しずつテーマの異なる(一部同じ内容の実験も含む)講座を行うことで都合の良い日程を自由に組み合わせて選んでいただきました。多くの回で、おおよそ予定した募集人数の方にお越しいただきました。参加者の(お子様を含めての)モチベーションの高さも相まって、サイエンスカフェという企画が本来目指している「研究者と一般市民が別け隔てなく討論する」という形に近いものができ、たいへん有意義で満足度の高い内容になったと自負しております。
5日間の連続講座でありましたが、夏休みの期間中の主に週末に開催し、少しずつテーマの異なる(一部同じ内容の実験も含む)講座を行うことで都合の良い日程を自由に組み合わせて選んでいただきました。多くの回で、おおよそ予定した募集人数の方にお越しいただきました。参加者の(お子様を含めての)モチベーションの高さも相まって、サイエンスカフェという企画が本来目指している「研究者と一般市民が別け隔てなく討論する」という形に近いものができ、たいへん有意義で満足度の高い内容になったと自負しております。
 1回目(7/25)と2回目(8/01)は、主として小学校高学年を対象として想定し、実験や説明を計画しました。そこで、いきなり液晶の話をする前に、氷(水)やドライアイスを観察することで、「物質の三態」、すなわち、学校で習うところの「固体」「液体」「気体」の状態変化について説明しました。とくに、このサイエンスカフェではコーヒーではなくジュースとアイスクリームを用意しており、その冷媒として使うドライアイスをみんなに配っていくつかの簡単な実験を行ない、身近で楽しいモノとして感じ取ってもらいました。さらに、液体窒素をみんなのビーカーに配布し観察しました。参加者の皆さんは、液体窒素を使って実験をするのははじめてということで、低温でも「沸騰;気化=液体→気体への相転移」が起こるということが、なんか不思議に感じているようでした。
1回目(7/25)と2回目(8/01)は、主として小学校高学年を対象として想定し、実験や説明を計画しました。そこで、いきなり液晶の話をする前に、氷(水)やドライアイスを観察することで、「物質の三態」、すなわち、学校で習うところの「固体」「液体」「気体」の状態変化について説明しました。とくに、このサイエンスカフェではコーヒーではなくジュースとアイスクリームを用意しており、その冷媒として使うドライアイスをみんなに配っていくつかの簡単な実験を行ない、身近で楽しいモノとして感じ取ってもらいました。さらに、液体窒素をみんなのビーカーに配布し観察しました。参加者の皆さんは、液体窒素を使って実験をするのははじめてということで、低温でも「沸騰;気化=液体→気体への相転移」が起こるということが、なんか不思議に感じているようでした。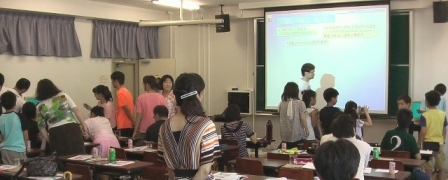 一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷えてくると「液晶テレビ」に戻り、 「液晶テレビをとかす」ということの意味を、みなさん納得されたようです。
一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷えてくると「液晶テレビ」に戻り、 「液晶テレビをとかす」ということの意味を、みなさん納得されたようです。
 つづいて、液晶テレビの仕組みがどのようになっているか、ごく簡単に解説し、その中で重要な要素である「偏光」について、実験を交えて学びました。みなさんに偏光板を配布して、光の通り具合を観察してもらったあと、セロテープを使って簡単な液晶テレビの原理となるものを作成し、光の透過具合を観察しました。
つづいて、液晶テレビの仕組みがどのようになっているか、ごく簡単に解説し、その中で重要な要素である「偏光」について、実験を交えて学びました。みなさんに偏光板を配布して、光の通り具合を観察してもらったあと、セロテープを使って簡単な液晶テレビの原理となるものを作成し、光の透過具合を観察しました。 これが乾くまでの間にということで、ドライアイスの入った箱にしゃぼん玉を入れてみることで、ドライアイスは二酸化炭素の固体から空気とは異なる重たい気体に変化したことを観察しました。さらに、エタノールと液体窒素を使って、「ガラス状態」についての実験をしました。1回目にも参加された方にとっては、物質の状態変化についての良い復習になったと思いますし、全ての方にとって「液晶」や「ガラス」という状態についてしっかり考えることで、「物質の三態」について理解していただけたと思います。
これが乾くまでの間にということで、ドライアイスの入った箱にしゃぼん玉を入れてみることで、ドライアイスは二酸化炭素の固体から空気とは異なる重たい気体に変化したことを観察しました。さらに、エタノールと液体窒素を使って、「ガラス状態」についての実験をしました。1回目にも参加された方にとっては、物質の状態変化についての良い復習になったと思いますし、全ての方にとって「液晶」や「ガラス」という状態についてしっかり考えることで、「物質の三態」について理解していただけたと思います。
 さて、はじめに描いたカップの絵の具が乾いたところで、カップを手で温めると描いた絵がカラフルに浮かび上がってきて、みんなでちょっとした歓声をあげました。みなさん、デジカメや写メでご自分の作品を写真に撮っていましたが、うまく写すことが出来たでしょうか。じつは、光の当て方で写真の出来がかなり異なるのですが、それは原理を少し理解していただけたら判ったと思います。なお、それぞれご自分の作品は、皆さんにお持ち帰りいただきました。
さて、はじめに描いたカップの絵の具が乾いたところで、カップを手で温めると描いた絵がカラフルに浮かび上がってきて、みんなでちょっとした歓声をあげました。みなさん、デジカメや写メでご自分の作品を写真に撮っていましたが、うまく写すことが出来たでしょうか。じつは、光の当て方で写真の出来がかなり異なるのですが、それは原理を少し理解していただけたら判ったと思います。なお、それぞれご自分の作品は、皆さんにお持ち帰りいただきました。
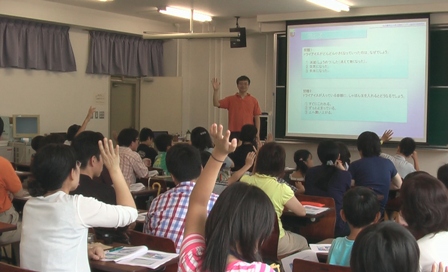 最後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しました。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、とても新鮮に感じていただけたようです。とくに、私たち生物の細胞膜などが液晶とたいへん関係が深いというのは驚きだと思います。
最後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しました。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、とても新鮮に感じていただけたようです。とくに、私たち生物の細胞膜などが液晶とたいへん関係が深いというのは驚きだと思います。
 まずは、液晶の基本である「物質の三態」、すなわち、学校で習うところの「固体」「液体」「気体」の状態変化について説明しました。今年の夏は猛暑で、このサイエンスカフェでジュースとアイスクリームを用意して食べながら進行するという企画は、ひじょうに喜ばれました。そして、その冷媒として使うドライアイスで簡単な実験を行ない、身近で楽しいモノとして感じ取ってもらいました。
まずは、液晶の基本である「物質の三態」、すなわち、学校で習うところの「固体」「液体」「気体」の状態変化について説明しました。今年の夏は猛暑で、このサイエンスカフェでジュースとアイスクリームを用意して食べながら進行するという企画は、ひじょうに喜ばれました。そして、その冷媒として使うドライアイスで簡単な実験を行ない、身近で楽しいモノとして感じ取ってもらいました。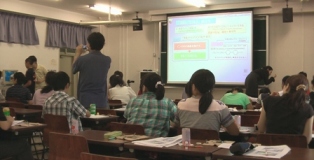 一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷えてくると「液晶テレビ」に戻り、 「液晶テレビをとかす」ということの意味を、みなさん納得されたようです。この実験は、何度やっても面白がられます。
一通り、液晶について分かったところで、それなら...ということで、液晶ディスプレイを温めたら、「液体テレビ」になって壊れてしまいました。でも、冷えてくると「液晶テレビ」に戻り、 「液晶テレビをとかす」ということの意味を、みなさん納得されたようです。この実験は、何度やっても面白がられます。
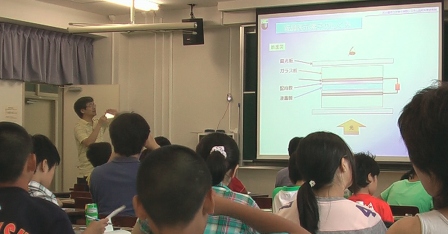 つづいて、液晶表示パネルの構造や原理について説明し、構成部品についていろいろな実験をしました。たとえば、ガラスの表面に透明電極(インジウムというレアメタルの酸化物)があると電気が流れることを実験で確認したり、偏光板を使って光がどのようになるかを2枚の偏光板を使って自分たちで実験をしながら、光の不思議な現象を体験しました。
つづいて、液晶表示パネルの構造や原理について説明し、構成部品についていろいろな実験をしました。たとえば、ガラスの表面に透明電極(インジウムというレアメタルの酸化物)があると電気が流れることを実験で確認したり、偏光板を使って光がどのようになるかを2枚の偏光板を使って自分たちで実験をしながら、光の不思議な現象を体験しました。 最後に、液晶パネル作成のなかでローテク部分といわれている「ラビング」という操作をまねた実験をやってみました。これは、薬品(PVAという洗濯糊のようなもの)が塗ってあるガラスの表面を擦る作業で、実際の製品となる大きなガラス板(マザーガラス)でもこのような作業が行われています。このようにして自分で「やや液晶TV」を作成し、これが光を通すことを確認したときには皆さん感動していましたが、この方法では均一なものはなかなか上手にはできないようです。
最後に、液晶パネル作成のなかでローテク部分といわれている「ラビング」という操作をまねた実験をやってみました。これは、薬品(PVAという洗濯糊のようなもの)が塗ってあるガラスの表面を擦る作業で、実際の製品となる大きなガラス板(マザーガラス)でもこのような作業が行われています。このようにして自分で「やや液晶TV」を作成し、これが光を通すことを確認したときには皆さん感動していましたが、この方法では均一なものはなかなか上手にはできないようです。
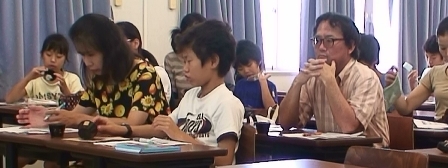 第2回に参加された方も若干いらっしゃいましたが、液晶インクは初めてという方が多かったので、今回もこれが「液晶インク」というものであることの紹介のみ行い、ネタばらしはしないで、絵の具のようなカラフルさが全くないインクでお絵かきしました。しかし、この日に限らず今年は連日の猛暑で、お絵かきをしている途中でも液晶インクが少し乾き始めると色が見え始めてしまい、ちょっと想定外でした。
第2回に参加された方も若干いらっしゃいましたが、液晶インクは初めてという方が多かったので、今回もこれが「液晶インク」というものであることの紹介のみ行い、ネタばらしはしないで、絵の具のようなカラフルさが全くないインクでお絵かきしました。しかし、この日に限らず今年は連日の猛暑で、お絵かきをしている途中でも液晶インクが少し乾き始めると色が見え始めてしまい、ちょっと想定外でした。
 これが乾くまでの間、虹を題材にして「光の波長と色」についてスライドを使って学びました。1回目にも参加者の皆さんに虹を描いてもらいましたが、この回に参加された方の多くは1回目に参加されていなかったので、もう一度描いてもらい、世の中(某公共放送や某学習塾など)に見られる「間違った虹」を紹介しながら、虹の原理を正しく理解するとともに、光の色とは何かを勉強しました。
これが乾くまでの間、虹を題材にして「光の波長と色」についてスライドを使って学びました。1回目にも参加者の皆さんに虹を描いてもらいましたが、この回に参加された方の多くは1回目に参加されていなかったので、もう一度描いてもらい、世の中(某公共放送や某学習塾など)に見られる「間違った虹」を紹介しながら、虹の原理を正しく理解するとともに、光の色とは何かを勉強しました。
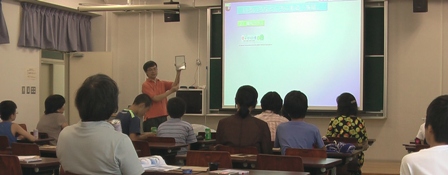 最後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しました。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、とても新鮮に感じていただけたようです。とくに、私たち生物の細胞膜などが液晶とたいへん関係が深いというのは驚きだと思います。
最後に、ディスプレイ以外の液晶の応用例をいくつか挙げ、愛地球博でのモリゾーゴンドラで使われた調光ガラスや液晶温度計などの話を実物を見ながら紹介しました。「液晶」が思いもしない様々なところで活用されていたり研究開発が考えられているとのことで、ふつうは液晶テレビのことしか知られていないので、とても新鮮に感じていただけたようです。とくに、私たち生物の細胞膜などが液晶とたいへん関係が深いというのは驚きだと思います。
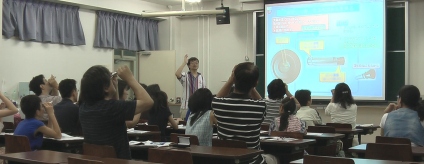 まずは、昨日の後半のテーマであった「分光=光を波長で分ける」の復習を兼ねて光の波長と色の解説を行いました。これを踏まえて、「直視分光器」を使って、自然光や蛍光灯やLED電球を観察した後、液晶画面を観察しました。現在の液晶のほとんどは、バックライトに蛍光灯を使っていますので、蛍光灯を見た時と同じような輝線スペクトルが観察されました。
まずは、昨日の後半のテーマであった「分光=光を波長で分ける」の復習を兼ねて光の波長と色の解説を行いました。これを踏まえて、「直視分光器」を使って、自然光や蛍光灯やLED電球を観察した後、液晶画面を観察しました。現在の液晶のほとんどは、バックライトに蛍光灯を使っていますので、蛍光灯を見た時と同じような輝線スペクトルが観察されました。
 つぎに、「加算混色」について優しく解説した後、パソコンにUSB顕微鏡を接続して液晶画面を見ると、光の三原色のブロックがしっかり見えました。また、高画質(高解像度)の液晶では、その一つ一つの大きさが小さく、カラー液晶画面の原理を説明されたことが自分の目で観察できました。より興味のある方には、終了後に実体顕微鏡をつかって、ご自分の携帯などの液晶画面を観察してもらいました。
つぎに、「加算混色」について優しく解説した後、パソコンにUSB顕微鏡を接続して液晶画面を見ると、光の三原色のブロックがしっかり見えました。また、高画質(高解像度)の液晶では、その一つ一つの大きさが小さく、カラー液晶画面の原理を説明されたことが自分の目で観察できました。より興味のある方には、終了後に実体顕微鏡をつかって、ご自分の携帯などの液晶画面を観察してもらいました。
 カラー液晶テレビの仕組みがわかったところで、「光を波長で分ける」と「光を足し合わせる」の組み合わせで色が出来上がっていることを、液晶テレビや液晶プロジェクタの光を「直視分光器」で観察することで、確認して理解していただきました。また、液晶プロジェクタでは、偏光が絡んでくるために、偏光板を使って手品(?)を行い、そのタネ明かし(原理の説明)をしました。これも、講座終了後に、何人かのお子さんが自分の偏光板を使って確かめていて、予想外に評判が良かったです。
カラー液晶テレビの仕組みがわかったところで、「光を波長で分ける」と「光を足し合わせる」の組み合わせで色が出来上がっていることを、液晶テレビや液晶プロジェクタの光を「直視分光器」で観察することで、確認して理解していただきました。また、液晶プロジェクタでは、偏光が絡んでくるために、偏光板を使って手品(?)を行い、そのタネ明かし(原理の説明)をしました。これも、講座終了後に、何人かのお子さんが自分の偏光板を使って確かめていて、予想外に評判が良かったです。
 また、今回の企画の方針として、親子参加型のサイエンスカフェ番外編を行うという趣旨から、冷たいジュース(または、お茶)と氷菓子を飲んだり食べたりしながら、堅苦しくならない雰囲気作りを心掛けました。途中で参加者と質問や議論をしたりすることを期待しましたが、なかなか実際には皆さんの発言を導き出すことは難しかったです。とは言うものの、記録的な猛暑だった「おかげ」で、この演出は大変好評だったようで(準備する方は汗だくでしたが)、アンケートを読ませていただいたところ、サイエンスカフェらしい講演会や授業とは違った雰囲気を味っていただき、満足していただけたと思います。たいへん暑い中を足を運んでいただき、参加された皆さんに感謝いたします。
また、今回の企画の方針として、親子参加型のサイエンスカフェ番外編を行うという趣旨から、冷たいジュース(または、お茶)と氷菓子を飲んだり食べたりしながら、堅苦しくならない雰囲気作りを心掛けました。途中で参加者と質問や議論をしたりすることを期待しましたが、なかなか実際には皆さんの発言を導き出すことは難しかったです。とは言うものの、記録的な猛暑だった「おかげ」で、この演出は大変好評だったようで(準備する方は汗だくでしたが)、アンケートを読ませていただいたところ、サイエンスカフェらしい講演会や授業とは違った雰囲気を味っていただき、満足していただけたと思います。たいへん暑い中を足を運んでいただき、参加された皆さんに感謝いたします。