

サイエンスカフェ in 名古屋
100回達成特別講演会
名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科では,市民との交流を通じて市民が科学技術に対する関心と理解を深めることに貢献する主旨で,2006年6月からサイエンスカフェを定期開催しています。この度100回目の節目を迎えたことを記念して,特別講演会を開催いたしました。
日時 : 2015年10月10日
会場 : 名古屋市立大学 さくら講堂(桜山キャンパス)
今年の10月10日は、3連休初日の初日であり、大安吉日であり、絶好の行楽日和となったにもかかわらず、講演会には260名を越える参加者がありました。郷先生のご講演やサイエンスカフェに対する市民の関心の高さの現れでしょうか。
会は郡理事長からの開会の挨拶により始まりました。サイエンスカフェを100回継続してきた事のほか、演者の郷先生が男女共同参画に尽力しておられることや、サイエンスカフェを行ってきたシステム自然科学研究科の教員が、学部をもたないので後進の教育をしていない(できない)ことなどにもふれておられました。
 次いで、山の畑事務室の森事務長から郷通子先生(情報・システム研究機構理事、名古屋大学理事、長浜バイオ大学特別客員教授)のご略歴の紹介があり、それに引き続き、物理学から生命進化学への道「タンパク質はモジュールからできている:機能と進化」と題して、郷先生の講演会が始まりました。
次いで、山の畑事務室の森事務長から郷通子先生(情報・システム研究機構理事、名古屋大学理事、長浜バイオ大学特別客員教授)のご略歴の紹介があり、それに引き続き、物理学から生命進化学への道「タンパク質はモジュールからできている:機能と進化」と題して、郷先生の講演会が始まりました。
郷先生は、講演の最初に、どんなことを楽しんできたかをお伝えしたい、とおっしゃっておられましたが、その言葉通り、先生の研究半生のお話は、研究の面白さが充分に伝わってきて、後進の若者にとって、すてきなメッセージになっていたと思います。
郷先生は、生物物理学のパイオニアとして研究をリードしてこられましたが、その原点は、大学生時代に聴かれた大沢文夫先生(当時、名古屋大学理学部)の集中講義にあるようです。この講義でワトソンとクリックが発見したDNAの二重らせん構造に興味を持たれ、大学院を大沢文夫先生の「生物物理学」講座へ進まれ、DNAを対象に研究を進められました。その後、海外留学中は、モデルペプチドの構造の理論的な研究を進められたそうです。
帰国後、九州大学の松田博嗣先生が主催する数理生物学講座に職を得て、自分自身のテーマを決めようとしたときに、影響を受けた事の一つに、留学していたときのコーネル大学の師であるシェラガ博士から言われた「これからはテーマを変えた方がよい。」という言葉であったそうです。「人との出会い」が研究にいかに大きな影響を与えるかを、改めて考えさせられた気がしました。しかし、これらの人々との出会いは、単なる偶然ではなく、郷先生自らが求めて飛び込んでいった結果の様に思います。
これからの生物学は、数学と物理学を使って発展するだろうという見込みに加えて、この数理生物学講座では、同僚たちが皆、理論物理屋さんで、それぞれが独立して自由に研究できる環境だったそうです。この研究室の自由闊達さが、郷先生ご自身の研究アイデアを育てることには欠かせない要素であったといいうことでしょうか。
さらに、当時は、研究を志す女性に対して大学の研究・教育ポストは少なく、郷先生も苦労されたそうですが、そのような当時を振り返って、「職のないときに、自分のアイデアを自由に考える時間がもてた。」と語っておられました。この前向きな思考も、研究を続ける上での大切な要素ではないでしょうか。
さて、郷先生は、遺伝子の本体であるDNAの構造に始まり、トリプレットコドンとタンパク質の構造の関係など、分子生物学の基本的な事を非常にコンパクトにわかりやすく説明してくださいました。それを書き記そうとすると、私の言葉ではとても長くなりうまく説明できないので、ここでは割愛させていただきますが、郷先生の最も著名な業績を要約すると、以下のようになるでしょうか。
タンパク質がいくつかの最小機能単位(モジュール)の組み合わせでできていることをヘモグロビンの立体構造解析(Go-plotと呼ばれる)により示し、さらに、それぞれのモジュールのつなぎ目には、対応する遺伝子にイントロンが存在する事を明らかにしました。ただし、このルールに従うとヘモグロビン遺伝子にはもう1カ所イントロンが存在することになるのですが、当時知られていたヘモグロビンの遺伝子にはそのようなイントロンが存在しませんでした。タイムリーな事に、郷先生の研究と相前後して、このようなイントロンの存在するグロビン遺伝子が他の生物で見つかりました。つまり、郷先生の「ここにイントロンが存在する。」という予言があたった事になります。このときの郷先生はとてもうれしかったに違いないと思います。このような発見こそが、研究の面白さであり、醍醐味ではないでしょうか。
その後も、イントロンの起源については決着がついてはいないけれど、他のタンパク質(バルナーゼやある種の転写調節因子)についても研究が進展しており、タンパク質がモジュール単位で機能を持っている事等が実証されています。
「設計図だけではわからない時、製品をみるとわかる。ずっとそうだった」と言っておられました。タンパク質とその設計図であるDNAの両方を研究対象にしておられた事が、イントロンの存在とタンパク質の機能的な構造単位の関係を見いだす事につながったと言えるように思います。
最後に、郷先生は、個人的経験からと前置きされた上で、サイエンスは女性に向いている。科学は、2つの意味で「やさしい」というお話をされました。まとめると以下のようになります。
- 「優しい」
- 女性が歓迎される
- 国の政策がバックアップ
- 選択肢の巾が大きい(発展性、基礎が応用に広がる)
- 「易しい」
- 積み上げが効く(地道な努力が実る)
- 学問体系が整っている
- 世界に共通(普遍的、性差がない、言葉の壁がない)
最後に、郷先生が名古屋大学に大学院生としておられたときに、キャンパスを歩いておられる髙橋禮子先生を見かけて、自分もこのような研究者になりたいと思ったとおっしゃっておられました。髙橋禮子先生は、糖鎖構造解析で著名な先駆的女性研究者ですが、東京女子高等師範学校(お茶の水女子大の前身)を卒業後、名古屋大学を経て、名古屋市立大学で定年退官まで教授を務められました。大学、大学院ともに郷先生の先輩にあたります。名古屋市立大学にもこのような有能な女性科学者がおられたのですから、これからも基礎科学と女性研究者を大切に頑張るようにとのエールをいただいたように感じました。
講演の後、選択的スプライシングはどのようにして決まっているかなど、会場からいくつかの質問があり、郷先生は、一つ一つ丁寧にお答えになっていました。また、その後の休憩時間にも高校生が質問に来るなど、充実した講演でした。
 第二部に先だって、「サイエンスカフェin 名古屋」を100回継続するにあたり、お世話になった3団体に対する表彰式が行なわれました。
第二部に先だって、「サイエンスカフェin 名古屋」を100回継続するにあたり、お世話になった3団体に対する表彰式が行なわれました。
名古屋市立大学がはじめてサイエンスカフェをはじめるにあたり、おしゃれな店を提供してくださっただけでなく、宣伝の仕方など、いろいろなアドバイスもくださったらくだ書店(代表取締役社長 外村英二氏)、名古屋市内16区の喫茶店を紹介してくださった愛知県喫茶飲食生活衛生同業組合(理事長 舟橋左門氏)、その後継続して会場としてセブンスカフェを提供してくださっている名古屋市文化振興事業団(理事長 平野幸久氏)に、感謝状と記念品が贈呈されました。
これらのセレモニーに引き続き、システム自然科学研究科の2先生が、人気のあったサイエンスカフェのポイントを30分で簡潔に説明しました。
 田上英明准教授は「生まれと育ち 〜遺伝情報の整理と活用〜」というタイトルで、エピジェネティクスの話題を提供しました。遺伝子に書き込まれている事ですべてが決まるのではないという事をとてもわかりやすく説明され、会場からは「自分も努力すれば報われるのでしょうか」と言ったような質問もいろいろと出てきて、講演会にも関わらず、サイエンスカフェ的雰囲気がよく出ていたと思います。
田上英明准教授は「生まれと育ち 〜遺伝情報の整理と活用〜」というタイトルで、エピジェネティクスの話題を提供しました。遺伝子に書き込まれている事ですべてが決まるのではないという事をとてもわかりやすく説明され、会場からは「自分も努力すれば報われるのでしょうか」と言ったような質問もいろいろと出てきて、講演会にも関わらず、サイエンスカフェ的雰囲気がよく出ていたと思います。
 また、三浦均准教授は、「水が凍ると熱がでる? 〜身近な物質、その結晶化の不思議〜」というタイトルで、水が氷になる時に周囲に対して熱を放出するという現象を中心に結晶成長の話題を提供されました。実際に金属板の上に置いた水滴を冷却しながら温度を測定し、氷ができた瞬間に周囲の水の温度が上昇する事を、聴衆の眼前で実演されました。このような演示実験を取り入れていることなど、私どもの提供しているサイエンスカフェの面白い理由が会場の皆さんにも納得していただけたのではないかと思います。
また、三浦均准教授は、「水が凍ると熱がでる? 〜身近な物質、その結晶化の不思議〜」というタイトルで、水が氷になる時に周囲に対して熱を放出するという現象を中心に結晶成長の話題を提供されました。実際に金属板の上に置いた水滴を冷却しながら温度を測定し、氷ができた瞬間に周囲の水の温度が上昇する事を、聴衆の眼前で実演されました。このような演示実験を取り入れていることなど、私どもの提供しているサイエンスカフェの面白い理由が会場の皆さんにも納得していただけたのではないかと思います。
これら2つのミニサイエンスカフェの内容は、以前に開催されたサイエンスカフェ in 名古屋の第78回と第92回とほぼ同じなので、詳しくはその開催報告を一読してください。
 しばしの休憩を挟み、第3部として「サイエンスカフェ in 名古屋の歴史」と題して、谷本英一名誉教授によるお話がありました。2006年6月に第1回を初めて開催するにあたり、大変お世話になった出口商店店主の出口豊氏のこと、以来、名古屋市内全16区の喫茶店で開催する事の大変さなどを振りかえり、話されました。話の後半は、「サイエンスカフェ in 名古屋」の歴史から離れて、ご自分の専門である「お茶」について、ご自身の体験も交えながら、「いかにすばらしい飲み物であるか」とか「カテキンの効能」などをサイエンスカフェ的雰囲気で話題提供されました。改めてサイエンスカフェ in 名古屋でじっくりと聴いてみたいものです。
しばしの休憩を挟み、第3部として「サイエンスカフェ in 名古屋の歴史」と題して、谷本英一名誉教授によるお話がありました。2006年6月に第1回を初めて開催するにあたり、大変お世話になった出口商店店主の出口豊氏のこと、以来、名古屋市内全16区の喫茶店で開催する事の大変さなどを振りかえり、話されました。話の後半は、「サイエンスカフェ in 名古屋」の歴史から離れて、ご自分の専門である「お茶」について、ご自身の体験も交えながら、「いかにすばらしい飲み物であるか」とか「カテキンの効能」などをサイエンスカフェ的雰囲気で話題提供されました。改めてサイエンスカフェ in 名古屋でじっくりと聴いてみたいものです。
終了予定時間を少々過ぎてしまいましたが、好評のうちにすべて無事終了しました。 ロビーでは、愛知県喫茶業生活衛生同業組合のご協力により、コーヒーと生ジュースを楽しむことができ、途中の休憩時間には、壁に掲載されていた100回分のサイエンスカフェ in 名古屋の写真とその開催報告を懐かしむ姿も見られ、結構にぎわっていました。
参加くださった皆様に感謝申し上げますとともに、今後ともご参加、ご支援くださいます様、よろしくお願い致します。
「サイエンスカフェ in 名古屋」委員会委員長
森山 昭彦
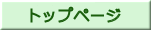
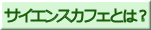
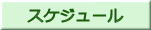
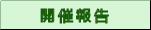


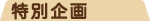

![[戻る]](images/back.png)