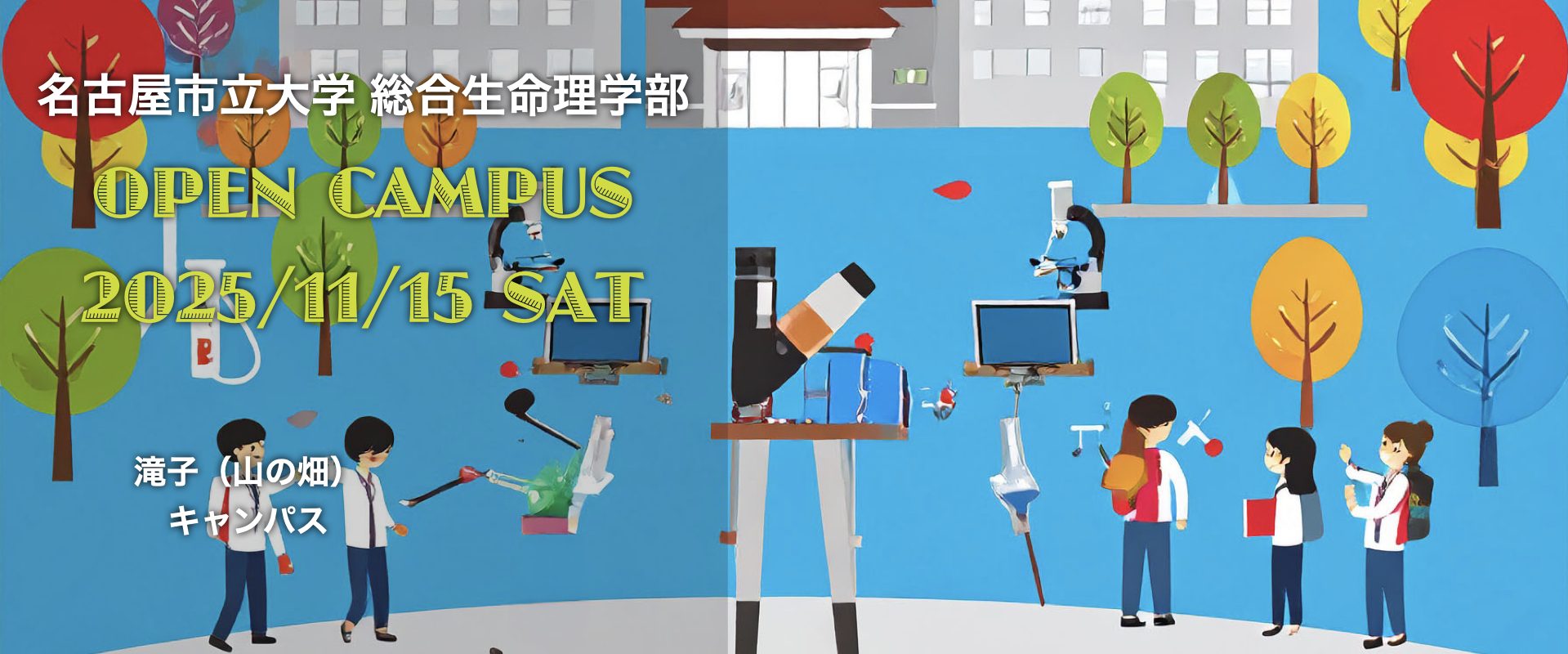インタビューをした日:2020年2月28日
インタビューをした人:総合生命理学部 学部生(二年)

総合生命理学部の学生の印象を教えてください。
元気で活発な学生が多い印象ですね。


総合生命理学部のいいところを教えてください。
この学部は、生物、物理、化学などが一学科にまとめられているため、いろいろな分野の授業を受けることができる。広く学ぶというのが、他では経験しにくいことだと思います。


研究者になったきっかけは何ですか?
子供の頃から考えるのが好きだったからです。小中高と上がってきて、普通校だったので大学に進学して…という感じで自然にですかね。


その研究分野を選んだきっかけは何ですか?
これがなかなか難しくて。例えば、宇宙に興味があるから天文学とか生き物に興味があるから生物学っていうのは分かりやすいと思うんですけど、画像処理って普通は小中高ではやらないので「よし、画像処理の研究者になるぞ」とはならないでしょう。僕の時代は高校で情報の授業がなかったけど、中学校の技術の先生がプログラミングができる人で、プログラミングの授業があって…「これはおもしろい」と思い、お年玉をはたいてソフトを買って、中高は自宅で自分でプログラミングをやっていました。そういう意味では、自分が得意な分野であり、あとは母親が美術の教員だったこともあり色に馴染みがあった、ということが重なって、結果大学院で画像処理の研究室に行き、自分に合っていたという感じかな。


ご自身の研究で大変なことは何ですか?
研究の重要な部分としてアルゴリズムの構築があります。これは単純作業を続けていたら自動的に結果がでるわけではなく、何かしらひらめきが必要なときがあるところかな。しかし、これが面白いんですけどね。


ご自身の研究の魅力を教えてください。
一つには、結果が分かりやすい。画像を処理してきれいになったり、見やすくなったりという結果が非常に分かりやすい。もう一つとしては、結果がどう応用されるかが分かりやすい。僕がやっているのは色覚バリアフリーですね。色覚異常者の人が見やすいように変換するということです。結果が出ると、社会の役に立つということが分かりやすい。アルゴリズムの構築では、画像をこう変換したいっていう目標があって、それを実現するための式を書くことになる。こうやりたいっていう言葉を式で表すときに、上手くいかないこともある。でも、それを修正して試すのはパソコンがあればいいから気軽にできる。家で思いついたらすぐにっていう感じでね。そういう、言葉を式で表すっていうのが面白いかな。


普段どのように研究を進めていますか?
まず一般的なことを言うと、論文を集めてきて、みんなが何をしていてどこまでできているのかを調べる。みんなが完璧なものを作っているわけではなく、たいてい何かが足りないってなっているので、それを実現するにはどうしたらいいかというのを考える。さっき言ったように、こうやりたいっていうのを実現する式を考えるわけで。蓄積のないものを考えるのは大変だけど、現代はみんな何かしらやっているので、他の人が何を考えているのかを知った上で、自分で何が足りないのかを見つけて上手くいくように変える、というのが多いですね。ただし、先行研究のない分野に行って自分が何かしら堀進めていくことも、もちろんやっている。それは実験結果を見ながら、ここはうまくいっているけどここは足りないというところを見つけて、もっと良くなるようにというのを繰り返しています。


次に先生ご自身のことについてですが、趣味は何ですか?
趣味ね。いろいろあるけれど、まあ音楽と将棋を出しときましょうか。相撲も好きだけど(笑)


音楽は聞く方ですか?
聞くのもあるし演奏もします。


何を演奏するんですか?
今はリコーダーをやっていて。


え!リコーダーですか?!
はい。リコーダーアンサンブルをやっています。リコーダーというと小学校でやることが多いと思うんだけど、大人の趣味のアンサンブルグループがあって、それに参加しています。今は新型コロナウイルスの影響で活動を自粛していますが。


そうなんですね!意外でした(笑)では次に、休日の過ごし方を教えてください。
今は100%子どもの相手です。子どもが2歳で、電車とか乗り物が大好きなので、地下鉄やバスに連れていくという(笑)


先生の学生時代はどのような感じでしたか?
大学の学部は物理学科でした。ちなみにリコーダーは大学のサークルから初めた。高校は吹奏楽部で、大学になってリコーダーアンサンブルというのがあって、それが今でも。リコーダーってこじんまりできるので、そういう意味では続けやすかったかな。あとはやっぱり勉強して…学生の頃はどこか旅行に行ったりとかはなかったですね。ひたすら家と大学を往復していました。


人生を四字熟語で表すと何になりますか?
四字熟語ではないですが…「人間万事塞翁が馬」ですかね。


最後に、先生が理学部生に求めることは何ですか?
自分が教務委員長ということもありますが、この学部はできてまだ3年目なので、毎年全てが初めてで、学生と教員で作っていくような状態にあるわけです。結構積極的にやってくれる人もいて、いい風にしたいなということをもちろん思っています。いろいろ学べることがこの学部のいいところなんですけど、最終的にはどこかの研究室に入って卒論を書いて、もっと行く人は院に行く。だから、常にずっと全部やるっていうのは無理なわけで、どこかで上手く絞っていかなくてはいけないんですよね。入学した時はまだ決まってなくていい。生物にしようか化学にしようか、もっと言うと生物と物理で迷うというのが許されるのがこの学部のいいところなんですけど、学年進行に従って、段々自分の興味を絞っていかなくてはいけない。多くの大学では、入学時や2年や3年になるときに強制的に学科に分けられるので、分けられたらそれをやるしかない。しかし、この学部にはそういう強制力がなく、自分でやらなければいけない。2年後半くらいからは決めていかないと厳しい。3年後期からは研究室配属が始まるので、それをちゃんと考えてほしいと思います。


ありがとうございました。