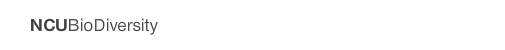生物多様性コラム(第4回)
ヒガンバナ
(学名:Lycoris radiata)
2013.10.1
 ヒガンバナの蕾 9月になると花茎だけが伸びてきて、決まってお彼岸の頃に咲く赤い花。花さえ咲いていれば、まず見落とすことはない。山の畑キャンパスでも100~200株くらいは咲いているので、登下校時に見たことのある人も多いだろう。後から葉だけが茂り、翌年5~6月頃に地上部は枯死する。
ヒガンバナの蕾 9月になると花茎だけが伸びてきて、決まってお彼岸の頃に咲く赤い花。花さえ咲いていれば、まず見落とすことはない。山の畑キャンパスでも100~200株くらいは咲いているので、登下校時に見たことのある人も多いだろう。後から葉だけが茂り、翌年5~6月頃に地上部は枯死する。
1000個もの別名を持つとされるが、中でもマンジュシャゲ(曼珠沙華)は古い呼び名で、サンスクリット語のmanjusakaに由来する。個人的にはこの呼び名が好きであるが、こう呼ぶと年配の私としては山口百恵の歌を思い浮かべる。正岡子規の『曼珠沙華』という短編小説を思い浮かべる人は、かなりの文学通であろうか。木下利玄の「曼珠沙華一むら燃えて秋陽つよし そこ過ぎてゐるしづかなる径」という短歌は、子どもの頃に国語で習っただけなのに私の心に今も焼き付いている。あの強烈な花の赤さ故なのか。 咲きかけの花 さて、この花の一番の特徴は、決まって秋のお彼岸の頃に花を咲かせるということである。どのようにして季節を察知するのか。植物生理学的には、花の咲く時期は日照と気温により影響されることになっている。日照時間は葉により感知され、ある一定の時間より短くなると花芽が形成される植物を短日植物という。日照時間が長くなると花芽ができるものは長日植物、日照に関係なく花芽ができるものは中性植物、このような現象を光周性という。
咲きかけの花 さて、この花の一番の特徴は、決まって秋のお彼岸の頃に花を咲かせるということである。どのようにして季節を察知するのか。植物生理学的には、花の咲く時期は日照と気温により影響されることになっている。日照時間は葉により感知され、ある一定の時間より短くなると花芽が形成される植物を短日植物という。日照時間が長くなると花芽ができるものは長日植物、日照に関係なく花芽ができるものは中性植物、このような現象を光周性という。
ヒガンバナでは、球根内での花芽の分化は葉が生育中の4月下旬に始まり、葉が枯れた6月中旬が雌ずい形成期、8月下旬に花粉形成期を迎え、9月中旬に開花する。しかし、夏の高温は花芽の発育を抑えるため、9月中・下旬にならないと花は咲かない。寒さの早く訪れる関東から関西へ向けて順次開花するのも理解できる。また、冬期に寒さを経験させないと、夏も葉をつけたまま、花芽も分化しない。つまり、一度は寒さを経験することが花芽分化に必要であり,このような性質は春化と呼ばれる。 開花した花 原産地の中国のヒガンバナは、二倍体(2n=22)で種子ができる。有史以前に渡来した帰化植物と考えられるニホンのヒガンバナは、三倍体(2n=33)であり、種子ができない。種子ができないということは、誰かが球根を植えてやらなければ、広まっていかないということである。人里を離れては全く見かけることがないことは、この花が人為的にひろまっていったことを物語っているのだろう。(村落や都市など、人間の生活圏に限って出現する植物を「人里植物」と呼ぶ。)
開花した花 原産地の中国のヒガンバナは、二倍体(2n=22)で種子ができる。有史以前に渡来した帰化植物と考えられるニホンのヒガンバナは、三倍体(2n=33)であり、種子ができない。種子ができないということは、誰かが球根を植えてやらなければ、広まっていかないということである。人里を離れては全く見かけることがないことは、この花が人為的にひろまっていったことを物語っているのだろう。(村落や都市など、人間の生活圏に限って出現する植物を「人里植物」と呼ぶ。)
鱗茎はリコリン やガランタミンと呼ばれるヒガンバナアルカロイドを含む有毒植物だが、何回も水に晒すと澱粉がとれるので、昔の人は救荒植物として田の畦や土手、墓地周辺などに植えて飢饉に備えたという。トンネルを造るモグラが住みつかないように、植えたという説もある。誤食した場合は、睡眠作用、痙攣、吐き気、下痢等の症状が現れるとされており、素人は食しないのが賢明であるが、古来、石蒜(せきさん)という生薬として肩こり、浮腫、乳腺炎の治療に用いられてきた。それよりも、ヒガンバナアルカロイドは、鎮痛、抗ウイルス、抗マラリア、抗腫瘍、中枢神経作用などが報告されており、いつか新薬が開発されるかもしれない。
(自然薯子)