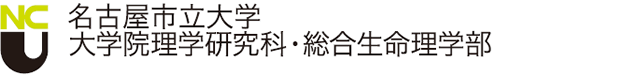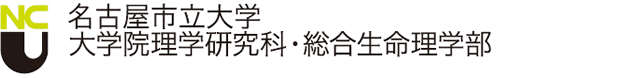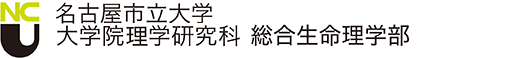杉谷 光司スギタニ コウジ

- 居室
- 滝子(山の畑)キャンパス 4 号館 2 階
- sugitani@nsc.nagoya-cu.ac.jp
- 電話
- 052-872-5846
- FAX
- 052-872-3495
- URL
- https://www.nsc.nagoya-cu.ac.jp/~sugitani/

- 生年
- 1958年
- 所属
- 自然情報系・教授
- 略歴
- 1982年 名古屋大学 理学部物理学科 卒業
1984年 名古屋大学大学院 理学研究科宇宙理学専攻 博士前期課程 修了
1987年 名古屋大学大学院 理学研究科宇宙理学専攻 博士後期課程 修了
1987年 名古屋市立大学 教養部 助手
1990年 ケルン大学(ドイツ) 第 1 物理学学科 客員研究員(~1991年3月)
1992年 名古屋市立大学 教養部 講師
1993年 名古屋市立大学 教養部 助教授
1996年 名古屋市立大学 自然科学研究教育センター 助教授
2000年 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 助教授(兼務)
2002年 大学院部局化により、名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 助教授
2006年 名古屋市立大学大学院 システム自然科学研究科 教授 - 学位
- 理学博士(名古屋大学)
| 専門分野 | 天文学、光赤外線・電波観測 |
|---|---|
| 研究キーワード | 星形成、星団形成、惑星形成、分子雲、観測天文学 |
| 担当科目 | (大学院)天体物質環境論、 天体物質特論 (学部等)宇宙の構造と進化、物理学基礎 |
| 最近の研究テーマ | (1) 惑星形成の研究: 惑星は、前主系列星(Tタウリ型星)が主系列星に進化する過程で、Tタウリ型星に付随する原始惑星系円盤の中で誕生すると考えられています。すばる望遠鏡、ハワイ大学2.2m望遠鏡、野辺山ミリ波干渉計などを用いて、原始惑星系円盤の研究を赤外線・可視光・電波の観測により行っています。また、私たちのグループがハワイ大学2.2m望遠鏡用に製作した広視野グリズム分光撮像装置(WFGS2)を用いて、上記観測のターゲットになるTタウリ型星の探査、原始惑星系円盤の構造に起因するTタウリ型星の変光、原始惑星系円盤からの質量降着に起因するHα輝線の変化などを調べています。 (2) 星形成の研究: 星や星団は分子雲の密度が高い所で誕生します。赤外線・可視光・電波の観測データを用いて、星の形成の環境や過程、形成された星の質量、星形成が周囲の分子雲に与える影響などを調べています。特に、大質量星が形成された結果、その周囲の分子雲で星が誘発形成される星形成(トリガー星形成)の研究 に力を入れています。星形成の研究には、主に私が開発メンバーとして関わっている南アフリカ1.4m 望遠鏡(IRSF)/3色同時撮像カメラ(SIRIUS)やハワイ大学 2.2m 望遠鏡を用いて近赤外線や可視光の観測を、野辺山 45m 電波望遠鏡やミリ波干渉計を用いてミリ波の観測を行っています。 |
| 主な研究業績 | Deep Near Infrared Imaging toward Vela Molecular Ridge C-1: A Remarkable Embedded Clusterin RCW36, Astrophysical Journal, Vol. 614, pp. 818-826 (2004). Detection of Molecular Hydrogen Emission Associated with LkHα 264, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.55, pp.L77-L81 (2003). Interferometric Observations of the T Tauri Stars in the MBM 12 Cloud, Astrophysical Journal, Vol.586, pp.L141-L144 (2003). Four Probable T Tauri Stars in MBM 12, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.55, pp.L49-L52 (2003). Hα Emission Stars and Herbig-Haro Objects in the Vicinity of Bright-rimmed Clouds, Astronomical Journal, Vol.123, pp.2597-2626 (2002). Near-Infrared Study of M16: Star Formation in the Elephant Trunks, Astrophysical Journal Letters, Vol.565, pp.L25-L28 (2002). |
| 教員からの一言 | 国内外の観測装置を用いて、天体観測を実際に行ってみませんか。膨大な天文学データの中から誰も気づいていない事実を掘り出してみませんか。いろいろな分野からの応募を歓迎します。 |
| 学会活動 | 日本天文学会、アメリカ天文学会、国際天文連合、日本惑星科学会 |